知の共創プログラム
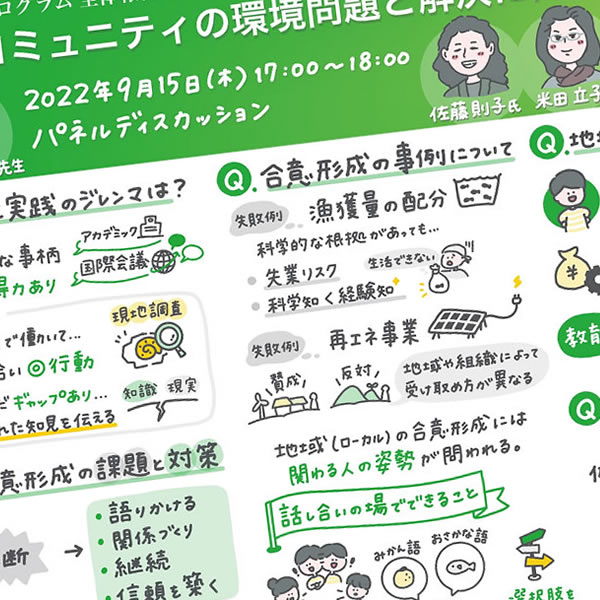
参加学生の声
山﨑 慶太(地球環境科学専攻)
企業の研究所を退職して一年後の四月から、「知の共創プロフラム」に参加させていただきました。在職中は、「電磁気学の建築空間への適用」や「木質バイオマスエネルギーの地域循環システムによる街造り」などをテーマに、統合的な普遍性事実を求め、現象を解析する実証科学的研究を続けてきました。退職後に歴史学や文学、西洋・日本芸術、気候学などを学び直し、俯瞰的に学問を見直してみると、自分が経験してきた「実証科学的研究から求めた統合的な普遍性事実だけで現象を解析し、社会に貢献できるか?」と疑問を持つようになりました。
年末の「知の共創プロフラム」の全体報告会に向けて、企業の一線、あるいは公的研究機関で活躍する、専門の異なる若い研究者と、webで月2回討論を進めていく中で、一企業の研究生活では得られない、「気づき」を得ることができ、この年齢で「科学的研究」と「人文・社会学的研究」の違いについても学ぶことができました。また、メンバ内で役割を決めたテーマ、「社会的インパクト評価の限界と可能性:地域における価値観」を報告した全体報告会でも、多分野の先生方から、専門分野に閉じこもっていたら得られない貴重な知見をいただくことができました。まだ、自分の研究の方向性は定まっていませんが、これらの様々なサジェッションを活かしながら、今迄とは全く異なるアプローチで、できれば、「科学的研究」と「人文社会学的研究」が融合した研究成果を目指したいと思います。
高橋 聖哉(社会環境学専攻)
昨今のさまざまな環境問題は、恒常的に身近な日々の生活に深刻な影響を与えています。企業活動をするにおいても、当然のように環境への配慮や責任が求められます。そのため、実務家としては、客観的な科学的根拠や価値規範を持ち備えたうえで発言や行動をするに越したことはありません。そして、社会や仕事でそれぞれ役割を持ちながらも、何らかのチームで課題へ挑み、解決していくことも多いと思います。
私にとっての「知の共創プログラム」とは、実際に今後影響すると予想される環境に対し、より高い視野や視座で捉え、挑むための重要なプロセスのひとつであり、アカデミックなスキルを身につける場です。また、環境学としての研究や学びが、分野横断型で「超学際的」という、幅広く新しい枠組みで習得できることは、実践知に役立つ非常に心強いカリキュラムと思い、志望しました。私は、新しい公共施設のあり方を、デベロップメント・プロパティマネジメントという仕事を通して、名古屋中心に活動しています。都市環境の将来適応策、地域やその活性化に資するためのコミュニティ形成について関心があり、それが研究テーマになっています。これらは公民連携などの都市政策に該当しますが、単に公共施設の再開発やリノベーション、空き家を埋めればよいわけでも形式知に当てはめればよいものでもなく、その地理の持つ歴史や文化資源、経済社会、地域の想いなど、広範囲から価値を判断する必要があります。研究を通して、その思考を深めていければと思っています。
中務 亜紀(社会環境学専攻)
電機メーカーで「使いやすさ」や「使い心地」を追求する人間工学関係の仕事に関わり、6年前にフリーランスとして独立しました。「ユーザーの理解」を深めようと他学の社会人コースの修士課程に入学し、地域の歴史とそこに生息する生きものをテーマに研究に取り組みました。またその頃から、業務として街なかを走行するロボットの検討に参加しています。知の共創短期プログラムに参加した当初は、まちの生きものとロボットのことを研究したいという漠然とした構想でしたが、さまざまな分野の先生方のお力を借り研究計画としてまとめることができました。ご自身の研究とあまり関連のなさそうな内容にも関わらず、熱心に相談に乗っていただき、ヒントをいただき、先生方の知識の広さと懐の深さに助けていただきました。
博士後期課程では、街なかに登場する自然物や人工物が人々に受容されるプロセスをテーマにしています。保護したくなる生きもの、駆除したくなる生きもの、利用してみたいモビリティ、いなくなってほしいモビリティなどの判断はどのようになされるのか、社会環境学という切り口から分析しようとしています。このような専門分野の枠を超えたテーマに取り組ませていただけるのは、文理の枠を超えた環境学研究科の知の共創プログラムならではだと感じています。まだ研究に着手したばかりですが、さまざまな分野の先生方や学生のみなさんから助言をいただきながら活動できることを、とても楽しみにしています。
吉田 大輝(社会環境学専攻)
自治体職員として働く中で、実務経験だけでは対応しきれない地域課題の複雑さを日々、痛感してきました。そこで、持続的な地域づくりに関する専門的な知識と研究力を高められるよう、「知の共創プログラム」に参加しました。働きながら学ぶことは簡単ではありませんが、先生、スタッフの方々の社会人学生への理解と柔軟なサポートにとても助けられています。
現在、自然との共生と地域資源マネジメントに関する政策提言に向けて研究を進めていますが、実務経験で感じた課題意識を出発点に、学術的な理論や先行研究を踏まえながら、現実に即した解決策を探る作業はとても刺激的です。研究の過程で得た知見は、職場での業務にも直結しており、実務と研究の両面で成長を感じています。
「知の共創プログラム」には、幅広いバックグラウンドを持つ学生が集まっており、多様な視点で議論が交わされます。一緒に修了を目指す学生たちから受ける刺激も多く、自分自身の視野を広げる良い機会となっています。先生方も実社会との接点を重視した指導をしてくださり、研究が単なる理論で終わらないよう常に問いかけてくれます。現場と学問を行き来するこの環境は、私にとってかけがえのない学びの場となっています。
ここで得た知識と経験を、地域社会の未来にもしっかりと還元していきたいと思います。

