知の共創プログラム
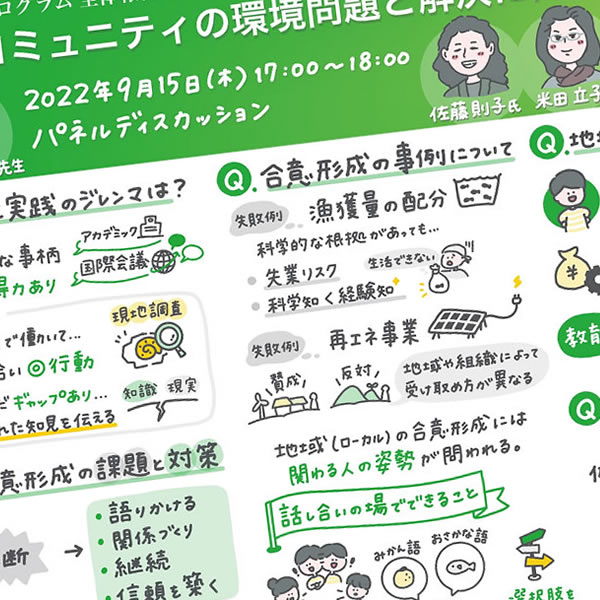
参加学生の声
小林 聡(社会環境学専攻)
「知の共創」のよさの一つは、専攻の異なる社会人の同期生と一緒になれることだと思う。コロキウムでは専攻外の研究にふれることができ、未知の領域の広がりに毎回大いに驚かされる。全体発表では、研究テーマが異なる同期生と共通のテーマを決めてそれぞれの分野から学際的な議論ができるように準備を進めるのであるが、自分とは異なる視点からのアプローチを目にすることになり、大いに刺激を受ける。また、専攻分野に依るかもしれないが博士課程は孤独な研究活動になりがちであるが、「知の共創」のメンバーは緩やかにつながっていて、ときどきSlakなどの雑談で情報交換がおこなわれ、実際にはこれがとても有用だと感じている。
私の研究は、分譲マンションの管理組合支援を仕事にしていることから、「問題解決型住民組織の形成要因」をテーマに掲げた研究で、簡単に言えば様々な困難に直面している高経年分譲マンションをどのようにすれば支援できるか、その方策を探っている。普通に社会人として仕事をしながらの研究活動で、実務で困難な状況に直面しながら先行研究を読み、研究データを集めて分析し、問題意識が変化し修正しなおすという試行錯誤の連続で、時間的に制約のある中で「長期履修制度」に支えられながら研究を続けています。
佐野 洋平(社会環境学専攻)
学士は法学、修士は法政治学、主に法哲学を学んだ。社会人では、市役所、PR会社、郷里に戻って、家業の魚市場、事業承継した伝統発酵食品製造業、同世代の仲間と設立したまちづくり法人、本学博士後期課程に入学、現在は市議会議員でもある。社会人院生に向けられた「知の共創プロフラム」は、地域社会人とアカデミアをつなぐまるでワームホールのような役割を果たしている。地域社会人として社会のさまざまな現場で実践をしながら同時にゼミナールやコロキウムで多様な学術分野の専門家と学びを共有できる。教員と同じ社会人院生と現役の大学院生とも気さくに意見交換もできる。地域に住み暮らしながら最先端の学問的空気を取込みながら研究ができる。
地方は、厳しい。大都市一局集中による諸々の流出は、地方の自由を奪っている。人的要因による自然環境変化は、地方の環境・コミュニティを蝕んでいる。地方のみの各々資本だけで元気になることは難しい。地方は都市と上手に付き合い、地域社会人は都市の専門知識人の最新の知恵と交わり地域をアップデートしなければならない。ワームホールをより活用しなければならない。「知の共創プログラム」には、人新世の時代の困難に立ち向かう持続的な社会変革の可能性の種を感じる。それが日々の喜びにもなっている。
石川 綾子(社会環境学専攻)
私は、名古屋大学の研究支援組織で、10年程、リスクマネジメント専門の研究支援人材として携わっています。一つの業務が、研究者が海外のバイオリソースを研究で用いる際のABS(Access & Benefit Sharing)です。業務経験のなかで、ABS制度の成立ちや運営について学術的な視点で深く調査・研究を実施したいと考え、名古屋大学環境学研究科の「知の共創プログラム」に応募しました。2022年、生物多様性条約の締約国会議(COP15)でデジタル塩基配列情報(DSIという)の利益配分(ABS)について、非常に大きな決定がされたことを受け、研究活動では、DSIの利益配分の国際的な取り決めの方向性について、国際関係論や科学技術ガバナンスの見地から検討しています。
知の共創プログラムでは、研究科の多様な専門分野の教員、行政機関、民間企業等で働いている受講生が意見交換をしながら研究を進めています。定期的な「公開コロキウム」では、研究テーマの発表を行い、多様な研究領域の教員及びバッググランドをもつ受講生から視点の違うコメントをもらうことで、研究の発展へ繋げることができました。また、「合同シンポジウム」では、受講生チームが決めた共通のテーマである「ウェルビーイング」を題材に、受講生の異なる環境での幸せや満足度について考察し、その多様性について検討することができました。「知の共創プログラム」では、仕事と両立しながら研究や勉強をできる環境や配慮が整っていますので、必ずや、仕事と学業両方について、相互に良い影響を与えながら発展していけるものと考えます。
岡田 美穂(社会環境学専攻)
私は、他学の社会人コースの修士課程から知の共創プログラムに応募しました。社会人学生を始めたきっかけは、勤めていた建設会社からの出向です。社外の組織に身を置く中で、過去の仕事で関わった湿地の環境保全について、会社から離れて研究したいと思うようになりました。そして、もう少し研究を続けたいと思い始めた頃に、参考にしていた本の多くを名古屋大学環境学研究科の先生方が執筆されていることに気づき、調べているうちに知の共創プログラムのことを知りました。
知の共創プログラムでは、行政機関、教育機関、企業、個人事業主、議員など、様々な立場で働いている方が仕事や家庭との両立に四苦八苦しながら研究を進めています。周りの方々と意見交換や困りごとの共有をしたり、先生の指導の下で一緒に社会課題を考えたりする経験は、自身の博士課程での研究テーマだけでなく、仕事や、仕事以外の活動をする上でも役立っています。この環境を生かして、のびのびと研究していきたいと思います。
櫻井 要(社会環境学専攻)
私の専門は栄養教育です。日本で管理栄養士を取得後、英国で栄養学修士相当として修了し、その後日本の教育機関に就職しました。栄養教育の一環である健康経営を研究テーマとし、博士号を取りたい気持ちはありましたが、なかなかコースや指導教員とのマッチングが上手くいきませんでした。そんな折、今の指導教員と知り合い、知の共創プログラムを教えていただいたことで応募に至りました。
社会人向けである知の共創プログラムでは、受講生のバックグラウンドが様々であることからその専門性も多様です。栄養学分野で学んでいれば知ることのなかった学問分野を受講生の研究発表を通じて学ばせていただいています。自分の研究についても、様々な視点からご指摘をいただくことで研究の足りないところに気づかせていただくことが多いです。論文執筆までの道のりは様々な苦労が伴いますが、貴重な学生生活をより充実したものにできるよう、これからも頑張りたいと思います。
三輪 晃司(都市環境学専攻)
参加の動機ですが、私は工学修士取得後すぐに会社員として働いており、いつかは専門性を磨いて博士号を取得したいと考えておりました。今回、様々な学問分野の教員と学生が超学際で交流ができる社会人向けのプログラムがあると知り、自費で受験を行い進学しました。ここで進学先の専攻では工学と環境学を選べましたが、現有の工学(自動車の燃費向上と排気ガス低減に繋がる技術開発とメカニズム解明に長年従事した知識の深化)ではなく、更なる知識の拡大(大気環境と労働環境の改善を個車単位ではなく社会全体の枠組みとして実装まで考えるための知識習得)を目指して、敢えて環境学を選択しました。
知の共創プログラムを受講した感想ですが、HP等の紹介にあるとおり実際に様々な分野の先生方から現有知識の範疇以外のご意見やご指導をいただけることと、社会人として多くの実務経験を積まれた学生の方々と交流ができることで時に先生方とは異なる知識と経験からも学べることの2点は、社会人学生という時間に制約があり、それなりに社会経験を積んだ身にとって、大変有意義かつ有効だと実感しております。
最後に、社会人学生の道を検討しており、視野を拡大したいと考えている方は、是非検討してみてはいかがかと思います。
大澤 康太郎(社会環境学専攻)
指導教員である三上先生の異動に伴い、同じく院生の片岡さんとともにこちらに編入学させていただいたのが2023年の秋になります。編入学と同時に知の共創プログラムに応募、採用していただいておりますが、定期的に他の院生の研究成果を知ることができ、また自分の研究成果をまとめる機会にもなっていて、大変感謝しております。
社会人院生として、また遠隔地に居住する院生として、先生や他の学生とのコミュニケーションの場があるというのがとても重要だと何度も感じています。知の共創はまさにそんな場で、各自の研究に関するディスカッションはもちろん、コロキウム発表をともにする仲間との学際的な議論、メンバーが加入しているslackでのやり取りなど、いい機会をたくさん持てています。
片岡 良美(社会環境学専攻)
わたしは、大学で技術専門職員として、研究における「可視化」の実務を担当しながら、社会人学生としては、環境問題の解決を目指す学際的な共同研究において、異分野研究者間のコミュニケーションがいかにして生じ、どのような意味で学問分野の垣根を超えた協働・融合がなされたのかについて研究しています。具体的には、わたし自身が参画する共同研究プロジェクトを対象に、そこでの経験をフィールドワークとして捉えることで、学際研究とは何かを検討しています。対象となる共同研究プロジェクトの一員でもありながら研究を行っているので、研究と研究する自分自身との関係について考えることが、研究上の問いを深める補助線でもあります。知の共創プログラムに参加して、参加学生の多くが、研究対象となる人々、事象、問題について、調査と被調査の関係だけでなく、多様な関係を築きながら向き合っていることが分かりました。こうした同士と、「研究者」兼「実践者」として直面する困難や、二つの立場を両立する/使いこなす工夫について議論できることは、わたしにとってとても刺激に満ちたものです。さらに、同じくフルタイムで仕事をしながら精力的に、かつ勢いをもって研究に取り組む先輩・同期に囲まれることで、やる気に火がつく環境だと感じています。

